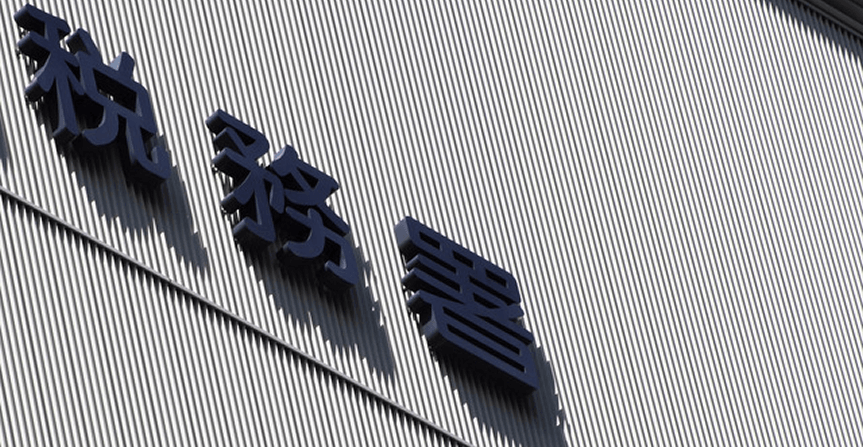お知らせ・ブログ
News&Blog
個人に対する貸付債権の相続税評価は?
2017.04.17
今回は、被相続人が知人に貸与していた金銭(貸付債権)が相続財産になるか否かで、相続人と税務署が争った事案をご紹介します。(平成24年9月13日裁決)
事案の内容
事案の内容は次の通りです。
- 被相続人Aはその知人H(個人)に対して、平成10年3月から平成15年8月までの間の多数回にわたり、総額1億7500万円の貸し付けを行い、その旨を内容とする公正証書を作成していた。
- AはHに対し、平成17年2月、貸付金の支払いを求める「催告書」と題する書面を送付した。その催告書に記載されている合計17回の寄託金及び貸与金の金額の合計額は、1億1790万円であった。
- 平成19年10月、Aが死亡し、その相続人らは平成20年8月に相続税の申告書を税務署へ提出したが、Hへの貸付金債権を相続財産として計上しなかった。
- 後日の税務調査において、Hに対する貸付金債権の申告漏れとして相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分が行われた。
- 相続人らは、Hに対する貸付金債権は存在しないか、存在したとしても回収が不可能又は著しく困難であるからその評価額は零円であるとして、相続税の更正処分の取り消しを求めた。
税務署の見解
税務署の見解は次の通りです。
- AとHは、金銭消費貸借契約等に係る公正証書を作成しており、また、AはHに対して催告書を送付していることから、Aを債権者、Hを債務者とする金銭消費貸借契約が存在し、貸付金債権が相続開始日に存在していたものである。
- Hは、税務署の調査担当者に対して、Aから約1億円を借り入れていること及び催告書記載の金額は多分間違いがないと思う旨の申述をしていることから、催告書に記載された1億1790万円が相続開始日における貸付金債権の元本であり、また、遅延損害金についても、Aに帰属する財産であると認められる。
- したがって、貸付金債権の相続開始日における金額は、元本1億1790万円であって、その遅延損害金は2,979,726円である。
- Hについては、相続開始日から、相続税の法定申告期限までの期間において、自己破産の申請をした及び破産宣告を受けた事実は認められず、評価通達205に定める破産の宣告等の事実がないことから、評価通達204に基づく貸付金債権の評価額は額面金額と同額である。
納税者の主張
一方の納税者の主張は次の通りです。
- 相続人は、本件相続開始日において、貸付金債権が存在したか否か及びその金額がいくらかについて全く認識していなかった。
- 税務署が認定を行った貸付金債権の有無及び金額については、AのHに対する催告書記載の金額の合計額であり、個別の確約書、預り書、受領書、借用書の原本の存在を確認したものではない。
- 債務者であるというHが税務署の調査担当者に多分間違いがないと思う旨の申述をしていることから相続開始日における貸付金債権の元本を認定しているが、そのような安易な認定は不当である。
- 評価通達205は、元本の価額に算入しない金額について、「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」と定めており、税務署が主張するように、自己破産の申請をした及び破産宣告を受けた事実が認められない場合には直ちに元本金額が確定するというものではない。
- 仮に、貸付金債権が存在するとしても、Aの催告に対してHが返済をしなかったのは、返済原資が存在しなかったというような事情があったためであるとも考えられる。
- Hの資産関係等を調査すれば貸付金債権について回収が困難な金額を評価することは可能であるにも関わらず、税務署はこれを行わず、評価通達に則った適正な評価を行っていない。
国税不服審判所の判断
最終的に国税不服審判所は次のような判断を下しました。
- 評価通達205に定める「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」には、債務者が個人である場合には、債務者の債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務を弁済するための資金を調達することができないだけでなく、近い将来においても調達することができる見込みがない場合も含まれると解される。
- 当審判所が調査したところによると、Hの職業は、釣り堀業となっており、また、Hは当審判所に対し、総合土木建設業で500万円位の所得がある旨の答述をしているが、平成18年分、平成19年分及び平成20年分の市民税は課されていない。
- また、h市の固定資産税《土地・家屋》課税一覧によれば、Hは、平成18年度にはh市内に宅地(固定資産税評価額約330万円)を有していたが、登記簿謄本によると、当該宅地は、平成18年11月22日に、譲渡担保が設定され、その後、第三者に所有権が移転している。
- 更に、h市内における金融機関等に対して、Hの取引状況等の調査を実施したところ、Aに対する借入金の返済が可能と認められる程度のH名義での預金残高は把握できなかった。
- このような資産状況等であるにも関わらず、Hは、少なくとも合計1億円程度のAからの借入金を有していたというのであるから、Hは著しい債務超過の状態にあったと判断するのが相当である。
- 次に、HがAからの借入金を返済するための資金調達が可能か否かをみると、相続開始日を挟んで3年分連続して市民税の課税実績がないことからすると、収入面からの返済原資は期待できないということができ、また、少なくともその住所地であるh市内に不動産を所有しておらず、返済原資となるような預貯金の存在も確認できない。そうすると、Hはその収入及び資産からみて被相続人からの少なくとも1億円程度も残っている借入金を返済するための資金を調達することは極めて困難であるということができる。
- 催告書を受け取った平成17年2月以降、HはAに対して借入金の一部でも返済した事実は認められず、また、AもHに対して貸付金の返済を受けるための何らかの手続(強制執行手続)を採った事実が認められないことからすると、Hに弁済能力がないことをAも認識していた様子がうかがわれる。
- 以上のことからすると、Hは、相続開始日においては、上記のとおり著しい債務超過の状態にあって、現にAに対する債務を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達することができる見込みがないというべきである。
- 従って、法令解釈に照らせば、AのHに対する貸付金債権については、評価通達205に定める「回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当するというべきである。
- そうすると、AのHに対する貸付金債権の評価額は「零円」となるのであるから、税務署の主張は採用することができない。
いかがでしょうか。
今回の事例は、貸付金債権に係る債務者に返済能力等が認められないことから、その貸付金債権の評価額は零円であると国税不服審判所は判断し、税務署が行った相続税の更正処分を取り消したというものです。
今後のご参考になれば幸いです。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
税理士法人レガートは、中央区銀座より様々な情報発信をしております!
税務に関するご相談、税理士をお探しのお客様は、お気軽にご連絡ください。
詳しくは「税理士法人レガート公式サイト」をご覧ください。